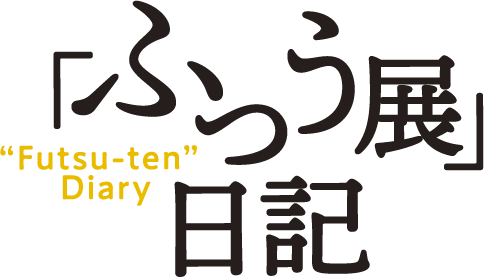途中で閉幕となった一昨年のふつう展でも、そして今回のふつう展でも、ポスターの主役は、土佐光起が描いた《伊勢図》です。ポスターの後に実物をご覧になって、あまりの小ささに驚かれた方も多いことでしょう。いつしかスタッフの間で「姫」と呼ばれるようになった作品です。

▲伊勢は、百人一首でも知られる平安時代の歌人。失恋の傷を癒やしに大和の国を訪れ、竜門寺というお寺に滞在して、滝を見て歌を詠んだエピソードを描いた作品です。
画面の縦の長さは、100.9センチ。その多くの部分が、墨だけで、しかも、かなりあっさり描かれています。ところが、「姫」だけが、くっきりと濃密に、色鮮やかです。薄暗くてほわっとした光景の中で、そこだけが、きりっと際立った美しさは、ありきたりの言葉ですが息をのむようです。
作者の光起は、江戸時代前期の土佐派の画家です。この派は、室町時代から続くやまと絵の派で、宮中の「絵所預」という役職をつとめてきました。社会的にはナンバーワンの地位にあった派といえるかもしれませんが、それだけでなく、日本独特の「やまと絵」の技術や美しさを代々守ってきた派です。そう考えると、今だったら芸術家としてだけでなく、伝統技術の保持者として注目されていても、おかしくないでしょう。
一昨年のふつう展の際、ポスターのデザイン案がデザイナーの島内泰弘さんから送られてきた時、本当に驚きました。実物は数センチほどの小さな「姫」の姿を、B2サイズのポスターにしようというデザインだったのです。「この作品を使ってデザインしてください」という依頼はしていなかったので、デザインを見た時、ほんの一瞬だけですが、「こんな作品あったっけ?」と思ったほどでした。次の瞬間には光起の《伊勢図》だとわかりましたが、実物の印象とはまた違う、絵としてのすさまじい完成度の高さを見せつけられる思いでした。

▲一昨年の「ふつうの系譜」展のポスター。
実物の印象しか頭になかった私には、およそ思いつかなかった作品の選択です。もしかしたら、デザイナーは、作品のデジタル画像を大きなディスプレイで一つ一つ拡大したりしながら、ポスターの主役を探したのかもしれません。現代の技術が、かつての名手の技と美の素晴らしさを教えてくれたような気がしますが、もし光起がこのデザインを見ても、きっと驚いたことでしょう。余談ですが、一昨年は、開幕後にその島内さんが実物の「姫」と対面して、その小ささに驚くのを楽しみにしていたのですが、展覧会は途中で閉幕となり、叶いませんでした。今年こそ、島内さんにも見てほしいものです。
ポスターになり、巨大化された「姫」を見ながら、日々、作者光起の巧みさに驚いていました。展覧会図録の文章でも紹介しましたが、光起は、自ら書いた秘伝書で、目や鼻を描く位置についての秘訣を記しています。ですが、それを知ったところで、細い筆の筆先を使って、目や鼻を、美しく、そしてイメージどおりの位置にちゃんと描くことなど、簡単にはできません。よほどの腕をもった人でなければ、筆を持つ手が震えたり揺れたりして、描けないでしょう。


▲「完璧」という言葉がぴったりな美しさです。
《伊勢図》の美しさがどうやって生まれたのか。もう一つのポイントが、彩色の技法です。
下の画像は、扇を持つ手の袖口のあたりの拡大写真です。「絵絹」と呼ばれる絵画用の絹に描かれているので、布目が見えます。左から、青色の部分、明るいベージュ色の部分、更に、朱色、ピンク色、少しピンクがかった白、普通の白が塗られ、一番右に暗い緑色の部分が見えます。この色の並びだけでも、とてもきれいです。
更に、青く塗られた部分に注目してみましょう。濃く見える部分と、薄く見える部分があるのがわかるでしょうか? 青い部分の形に沿って、濃いところがありますが、その内側は薄くなっています。

▲この写真の範囲は、実物では約1.5センチ四方です。
下の写真は、上の写真の一部分です。よくご覧ください。右の方の薄い部分では、青い絵の具は、格子状になった絹の糸の「向こう」にだけ見えています。つまり、絹の裏側から絵の具を塗っているのです。そして、濃い青のところは、絹糸にも色が着いていて、表側から塗られていることがわかります。

▲右の方は、絹目の向こうに絵の具が見えます。
恐らく、青く表す部分全体を裏から塗って、一段階濃く表したい部分だけ、表からも塗ったのでしょう。青の絵の具は、岩絵具の「群青」ですが、一種類の絵の具だけで、しかし、それを裏と表から塗ることによって、強弱のある美しさを作り出しているのです。裏側から塗るこの技法は、「裏彩色」と呼ばれています。


▲着物の「地」の部分を塗った後に、金や赤、緑や白で模様を描いています。
裏彩色といえば、近年、伊藤若冲の《動植綵絵》に使われていることがわかり、話題になりました。《動植綵絵》の場合は絹目がとても詰んでいるので、表から見ただけではわからず、修理の時にはじめて見つかりました。しかし、ご覧いただいたように、この光起の作品の場合は絹の目が粗いので、拡大写真やルーペを使えば、表からでもある程度わかります。
絹という、透けるような素材に描く場合、その特性を生かして裏からも色を塗るのは、平安時代の昔からごく普通のことでした。古代や中世の仏画の研究をしている人たちなどは、作品調査の時に、裏彩色にも注意して観察するのが普通です。私も、江戸時代の絵画を調査する時、裏彩色があるかどうかをできるだけ見るようにしていますが、たとえば、浮世絵師の菱川師宣の作品にも使われていた例があります。若冲や光起のすごさは、裏彩色を使ったことではありません。その手法をどんなふうに使って、どんな効果を出すのか、その技術の生かし方が素晴らしいのです。
江戸時代以前の日本には、あまり多くの色の絵の具はありませんでした。しかし、きれいな絵を描くには、色の数が多ければよいというわけではありません。少ない種類の絵の具を使って、工夫を凝らして、見事な「美しいもの」を作り上げる。光起の「色彩の精密感」が醸し出す美しさには、そんな平安時代から続く歴史が生きているわけです。


▲こうして見ると、裏彩色の青色にも、濃淡が付けられているのがわかります。
(府中市美術館、金子)